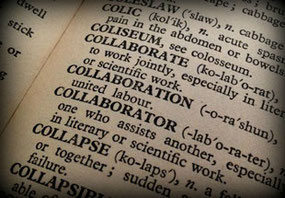いくつかの写真と青春時代のまぼろし
あちらもプロならこちらもプロ、という一枚が撮れた。
2019年1月、インドのデリーに行った。バルサアカデミー アジアパシフィックカップというサッカーの大会を観戦するためだ。品川大井町校のU−11チームで3番を背負う息子の応援に行った。
試合の合間、一服でもしようかと会場の外に向かうと、同じタイミングでルイス・ガルシアが関係者と一緒に歩いてきた。バルセロナの下部組織出身で、2003−04シーズンにはバルセロナでシャビやルイス・エンリケ、ロナウジーニョやラファエル・マルケス、フィリップ・コクーやマルク・オーフェルマルスとともにプレーしたレフティーは、ゲストとして大会に顔を出していた。
すぐさま英語で声をかけた。撮影の同意を得てシャッターを切った。何も言わずとも、ルイス・ガルシアはカメラに対してさわやかな笑顔を向けてくる。独占インタビューの記事にでも使えそうな写真を撮ることができた。握手もしてもらった。その間は10秒あまりだったと思う。我ながらよくやった。
メディア界のはしくれを行ったり来たりしているような15年があったからこそ、すぐさま一連の動きができたのだと思っている。背景に三角コーンが3本写り込んでしまっているのはご愛嬌。そのあと、息子がルイス・ガルシアから抜け目なくサインをもらったのもご愛嬌。
それから10日ほどして撮影した写真はミュージシャンのものだ。スコットランドのグラスゴーからティーンエイジ・ファンクラブが来日した。バンド結成30周年のアニバーサリーツアーで、東京、名古屋、大阪をめぐった。
前座は曽我部恵一。あえて曽我部くんと言いたい。この20年ほど、ずっと歌を聴き続けてきたし、勝手に身近な存在だと感じている。1995年に『若者たち』というアルバムを買って以降、曽我部くんとサニーデイ・サービスにはずっとぞっこんだ。家族全員で渡辺俊美さんとのライブを観に行ったこともある。前座はサニーデイ・サービスの名盤『東京』の「恋に落ちたら」で始まり、息子が好きだと言っていた「満員電車は走る」もやってくれた。
ティーンエイジ・ファンクラブもずっと聴き続けてきたバンドだ。グランジとネオアコの狭間を攻めるような曲はいつだって外れがない。アルバムのアートワークもいつだってかっこいい。1990年代にはニルヴァーナと並んで語られることも少なくなかったバンドは四半世紀以上たった今はもう、カート・コバーンのようにクールなロックンローラーというより音楽好きな好好爺という感じだった。それでも、というより、だからこそ、みずみずしい一曲一曲が胸に響いた。
曽我部くんとティーンエイジ・ファンクラブは否応なく青春時代を思い出させた。『東京』『愛と笑いの夜』『サニーデイ・サービス』『24時』あたりをよく一緒に聴いていた女の子とは2000年(その子と結婚する3年前だ)、渋谷公会堂に「LOVE ALBUM TOUR」を観に行った。その女の子の家に僕が朱色と白のポータブルのレコードプレーヤーを持ち込んでよく聴いていたのがティーンエイジ・ファンクラブだった。「そればっかり聴いてるよね」と言われたのは確か『ソングス・フロム・ノーザン・ブリテン』だったと思う。
そこから僕の記憶は横にそれてしまう。まだ僕たちが若者たちだったころ、ロフト付きの六畳のアパートの光景が見えてくる。申し訳程度のキッチンには窓がついていて、そこからふいに西日が差し込んでくる。まぶしすぎるほどではなかったけれど、出し抜けに光を浴びた女の子はどうしたはずみか泣き出してしまった。理由は聞かなかった。その女の子が誰だったのかは覚えていない。そんな出来事があったのかどうかも、本当はわからない。